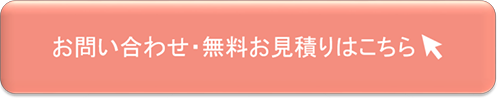感染症対策で注目される“高頻度接触部位”の清掃方法とは? ~手すり・ドアノブなど、コロナ後の清掃の新常識~
カテゴリ:ブログ

新型コロナウイルスの流行以降、私たちの生活や働き方はもちろん、施設における定期清掃の頻度や対象範囲にも大きな見直しが入りました。特に「高頻度接触部位」と呼ばれる、日常的に多くの人が触れる箇所の清掃・消毒は、感染症対策における最重要項目として注目されています。
しかし現場では、「どの場所を」「どのように」清掃すればよいのかが明確でないケースも多く、清掃の質に差が出ることもあります。この記事では、感染リスクを最小限に抑えるための重点清掃ポイントと、実践的な手順について詳しく解説します。
1. 高頻度接触部位とは? 見落とされがちな清掃ポイント
「高頻度接触部位」とは、不特定多数の人が日常的に手で触れる場所を指します。以下のような箇所が該当します
・共用部の手すり、ドアノブ、エレベーターボタン、インターホン
・会議室や休憩室のテーブル、椅子の背もたれや座面
・多機能トイレ内の操作パネル、洗浄レバー、手すり
これらの部位は目立つ汚れが少ないため見過ごされがちですが、ウイルスや菌の付着が多く、重点的な清掃が必要です。
2. 清掃と消毒の違い|混同しやすい2つの衛生作業
「清掃」と「消毒」は似て非なるものです。それぞれの役割は以下のとおりです:
・清掃:ホコリ、皮脂、食べこぼしなどの目に見える汚れを取り除く行為
・消毒:ウイルスや細菌などの病原体を不活化・除去する行為
汚れを除去せずに消毒剤を使用しても、ウイルスの除去効果は十分に発揮されません。清掃→消毒という順序を守ることが不可欠です。作業手順はマニュアル化し、誰が実施しても一定の衛生レベルを保てる体制を整えることが求められます。
3. 部位別|効果的な清掃・消毒の方法

部位や素材によって、適切な清掃・消毒方法は異なります。以下に代表的な部位ごとの対策を紹介します。
・金属製ドアノブ・手すり:アルコール消毒が効果的。ただし腐食防止のため、使用後は水拭きや乾拭きを行いましょう。
・タッチパネル・スイッチ類:精密機器専用の消毒クロスや静電気対策済の除菌スプレーを使用。直接スプレーせず、布に吹きかけてから拭き取ります。
・布張りの椅子・ソファ:除菌スプレー使用後は、しっかりと乾燥させることが必須です。湿気が残るとカビや雑菌の繁殖リスクがあります。
・トイレ内の操作パネル・洗浄レバー:塩素系消毒剤が有効ですが、素材への影響や臭いに注意。使用後の換気を徹底し、非接触型機器の導入も検討しましょう。
4. 頻度と記録|「やったつもり」を防ぐ清掃ルール
どれだけ丁寧な清掃でも、実施頻度が不十分では意味がありません。理想的な対策は以下のとおりです:
・1日2回以上、朝と昼、または昼と夕方など、時間を分けて実施する
・清掃ログやチェックシートを用いて「いつ・誰が・どこを」清掃したかを記録
・スタッフへの衛生教育を徹底。正しい手順や消毒剤の取り扱い、手指衛生なども教育内容に含めましょう
記録を残すことで、清掃の透明性が高まり、従業員全体の衛生意識の向上にもつながります。
5. 清掃業者に外注する際のチェックポイント
感染症対策を専門業者に委託する場合、以下のポイントを必ず確認しましょう:
・感染症対策に特化した清掃プランがあるか(頻度、清掃対象、使用製品など)
・使用する洗剤や消毒剤の明示、および清掃手順の提示があるか
・賠償責任保険への加入や、感染症対策に関する実績・事例があるか
これらの条件を満たす業者を選定することで、安心かつ継続的な衛生管理体制の構築が可能になります。
6. まとめ|高頻度接触部位対策は「見えない安心」を生み出す鍵
「高頻度接触部位」の清掃・消毒は、感染症の拡大を防ぐだけでなく、従業員や来訪者に対して「安心感」を提供する行為です。特にコロナ禍以降、衛生意識の高まりにより、施設の清掃品質がそのまま企業や運営者の信頼性に直結するようになりました。
清掃は単なる日常業務ではなく、施設全体の安全・安心を支える重要な柱です。今後も頻度や手順の見直し、記録の徹底、外部専門家の活用などを通じて、継続的かつ実効性のある衛生管理を実践していきましょう。